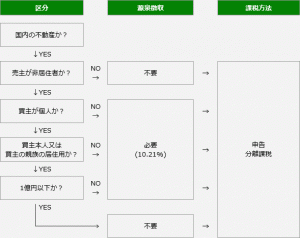非居住者の方が日本国内にある不動産を売却する場合の税金
2017/01/30
非居住者である方が、日本国内の不動産を売却する場合は、通常の売買とは異なる点が幾つか存在をします。
主に異なるのは税金面のことで、非居住者の方特有の手続きなどが必要です。
相続によって得た不動産であっても、相続人の方が非居住者であれば影響を受けてしまいます。
そのため、現在日本国内の不動産の売却を考えていらっしゃる方で、非居住者であるという方は要注意です。
今回の記事では、この非居住者の方が日本国内にある不動産を売却する場合の税金についてご説明致します。
それでは、まず本題の税金の話の前に、今回の記事で重要となる非居住者についてご説明致します。
目次
非居住者とは
非居住者とは、所得税法上の居住者以外の個人のことをいいます。
居住者には定義が定められており、それに該当をしなければ非居住者となります。
それでは、まず非居住者と判定をされる基準についてご説明致します。
非居住者と判定をされる基準
居住者と非居住者の定義は所得税法で定められており、主に下記の表の基準をもとに判定をされます。
| 納税者の区分 | 定義 | |
|---|---|---|
| 居 住 者 |
永住者 | 国内に「住所」を有し、又は現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人のうち、非永住者以外の個人 |
| 非永住者 | 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 | |
| 非居住者 | 居住者以外の個人 | |
上記の定義での「住所」とは、「個人の生活の本拠」のことをいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判定を行います。
また、「居所」とは「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」のことをいいます。
居住者と非居住者の判定に基本的に国籍は関係がありませんので、日本の国籍をお持ちの方でも、非居住者となってしまうことがあります。
複数の滞在地があり、外国でも日本でも居住者と判定をされる場合は、各国と日本との間に締結をされている租税条約によって、どこの国の居住者となるかを判定します。
(租税条約とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として主権国家の間で締結される成文による国家間の合意(条約)のことです。)
各租税条約によって判定基準は異なりますが、一般的に個人につきましては、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」、「国籍」の順に考えて判定をします。
滞在日数のみで判定をするものではなく、滞在日数が多い国の居住者となる訳ではありません。
例えば、米国税法上ではグリーンカードを保持していなくても、当該年度中「31日」以上米国に滞在し、かつ過去3年間の米国滞在日数の合計が「183日」以上の個人であれば、居住者と見なされます。
過去3年間の米国滞在日数につきましては、「その年における滞在日数+1前年の年における滞在日数×1/3+2年前の年における滞在日数×1/6」で算出を行います。
過去3年間で毎年「132日間」米国に滞在をしたのであれば、「132日+132日×1/3+132日×1/6=198日」となり、米国の居住者と判定をされます。
しかし、滞在日数の基準を満たしていても、客観的事実によって日本の居住者であると判定をされた場合は、日本の居住者となります。
これは、世界各国を旅して転々としていらっしゃる方にも該当をし、その人の「生活の本拠」が国内にあれば、日本の居住者となる場合があります。
こういった定義であるため、やはり、外国人の方は非居住者と判定をされる可能性が高くなってしまいます。
反対に、ずっと日本に住んでおり、1年間のうち海外に数日間旅行へ行く程度の方は、殆どの場合日本の居住者となります。
以上が、非居住者と判定をされる基準についてとなります。
非居住者となってしまった場合は、居住者であった時とは異なる点が幾つか存在をします。
主に、影響を受けるのは税金面であり、非居住者となった場合は注意が必要です。
そのため、次は居住者と非居住者の異なる点についてご説明致します。
居住者と非居住者の異なる点
居住者から非居住者となった場合は、税金面で大きな変化があります。
居住者と非居住者では課税対象が異なり、場合によっては、納付をする税額が大きく変化します。
居住者と非居住者の課税対象の違いは、下記の表の通りとなります。
| 納税者の区分 | 課税所得の範囲 | |
|---|---|---|
| 居 住 者 |
永住者 | 国の内外で生じたすべての所得 |
| 非永住者 | 国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金された所得 | |
| 非居住者 | 国内源泉所得 | |
このように、非居住者の方は、日本国内で生じた「国内源泉所得」のみが課税対象となります。
「国内源泉所得」のみということは、その範囲以外のものは、課税をされなくなるということです。
「国内源泉所得」の範囲につきましては、下記の通りとなります。
- 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得
- 国内において組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
- 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
- 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。 - 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
- 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
- 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
- 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
- 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
- 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
- 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
- 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
- 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
- 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
なお、非居住者の方が「恒久的施設」を有している場合、その種類によって課税関係が異なります。
非居住者は、その人が国内に恒久的施設を有する場合は、居住者と同様に(一定の所得は源泉徴収が必要)原則は申告納税方式となります。
その他の場合には、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式となります。
「恒久的施設」は「PE(PermanentEstablishment)」と言われることもあり、影響を受けるものは下記の3つとなります。
- 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
- 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
- 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
恒久的施設を有するかどうかを判定する際には、形式的に行うのではなく、機能的な側面を重視して判定を行います。
例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は「恒久的施設」と判定をされますが、単なる製品である冷蔵庫などは「恒久的施設」と判定をされません。
なお、居住者の方は、1年間に一定の所得があった場合は、所得税と共に住民税(所得割+均等割)の支払義務も発生をします。
一定の所得金額につきましては、市区町村で規定が異なりますが、ある程度大きな所得があれば、殆どの場合支払義務が発生をすることになります。
住民税は、1月1日時点で市区町村に住所がある方で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税(所得割)をされます。
そのため、非居住者の方は所得を得た時期によっては、住民税が不要となる場合があります。
例えば、平成27年3月に海外勤務者として出国をする場合、平成28年1月1日時点に日本国内に住所がありません。
その場合は、前年に所得があったとしても、平成28年度の住民税は課税をされません。
ただし、日本国内に事務所、事業所、家屋を所有している場合は、均等割のみ課税をされます。
また、平成27年3月に出国をして非居住者となっても、平成27年のうちに帰国をして平成28年1月1日に住所を所有する場合は、支払義務が発生をします。
やはり、こういった税金面のことは、事前に知っておかないと後にトラブルになりかねません。
ご自身の信頼に関わってくるものですので、いい加減にしないように注意が必要です。
なお、租税条約で国内源泉所得の種類や課税関係などが異なっている場合は、そちらを優先して適用することになります。
そのため、上記の国内源泉所得や課税関係などが適用をされない場合もありますので、この点にはお気を付けください。
以上が、居住者と非居住者の異なる点についてとなります。
非居住者の方が日本国内の不動産を売却する場合は、上記の国内源泉所得となります。
国内源泉所得となるということは、日本で確定申告と納税を行う必要があります。
非居住者の方が不動産を売却する時は、原則として源泉徴収が必要となり、その後、期間内に確定申告を行って納税をします。
なお、先程も申し上げましたように、国内源泉所得や課税関係などは租税条約によって異なることがあります。
そのため、一概にこれからご説明させて頂く内容が正しい訳ではありません。
租税条約によって異なる規定があるようでしたら、そちらを優先して適用してください。
それでは、まず非居住者が不動産を売却した時の源泉徴収についてご説明致します。
源泉徴収について
非居住者の方が不動産を売却する場合は、源泉徴収をされることがあります。
源泉徴収を行う必要がある場合は、期限内に一定の金額を所轄の税務署、又は、最寄りの金融機関に納付します。
なお、源泉徴収で厳密な税額を納める訳ではありませんので、後に確定申告を行わなくてはいけません。
それでは、まず源泉徴収が必要となる条件についてご説明致します。
源泉徴収が必要となる条件
非居住者の方が不動産を売却した時には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければいけない場合があります。
個人が不動産を売却する場合では、一定の条件を満たしていれば、源泉徴収を行う必要はありません。
源泉徴収が不要となる条件は、下記の通りとなります。
- 買主の方が個人である
- 買主本人、又は、その親族の居住の用に供する不動産である
(親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます) - 不動産の譲渡対価(譲渡価額)が1億円以下である
(不動産が共有の場合は、共有者ごとにその持分に応じて1億円を超えるかどうかの判定を行います)
このように、条件が3つ全て揃っている方は、源泉徴収を行う必要はありません。
下記の図の流れで判定を行えますので、参考にしてください。
(源泉徴収が必要で申告分離課税の場合)
上記の図から辿っていき、源泉徴収が不要となった場合は、源泉徴収を行う必要はなく、期間内に確定申告をして納税を行ってください。
源泉徴収が必要となった場合は、源泉徴収を行った後、こちらも期間内に確定申告をして納税を行ってください。
なお、手付金や中間金であっても、それが不動産の譲渡対価(譲渡価額)に充てられるものである場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。
また、不動産の譲渡対価(譲渡価額)は、譲渡所得とは異なりますので、混合して間違わないようにお気を付けください。
「譲渡対価(譲渡価額)」は不動産を売却して得た総収入金額であり、「譲渡所得」は「譲渡対価(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で求められた金額です。
源泉徴収が必要かどうかの判定では、「譲渡対価(譲渡価額)」のほうを基準とします。
以上が、源泉徴収が必要となる条件についてとなります。
源泉徴収が必要であった場合、納付をする金額は、比較的簡単な計算で求めることが可能です。
譲渡対価(譲渡価額)と税率さえ知ることができれば算出が行えますので、ご自身でもすぐに計算を行うことができます。
それでは、次は源泉徴収をされる金額についてご説明致します。
源泉徴収をされる金額
源泉徴収をされる金額についてですが、こちらは確定申告時と計算方法が異なります。
確定申告時には、定められている税率を譲渡所得に乗じて、税額を算出します。
源泉徴収をされる税額は、定められている税率を譲渡対価(譲渡価額)に乗じて算出を行います。
このように、源泉徴収の時は譲渡所得ではなく、譲渡対価(譲渡価額)に税率を乗じるだけですので、確定申告の時よりも計算を行いやすいです。
実際に、源泉徴収をされる税率と金額例につきましては、下記の表の通りとなります。
| 源泉徴収の税率 | 10.21% (内0.21%は復興特別所得税) |
|---|---|
| 譲渡対価が 「100万円」の場合 |
102,100円 (100万円×10.21%) |
| 譲渡対価が 「200万円」の場合 |
204,200円 (200万円×10.21%) |
| 譲渡対価が 「300万円」の場合 |
306,300円 (300万円×10.21%) |
このような形で算出を行いますので、特に複雑な計算を行う必要はありません。
譲渡対価(譲渡価額)から源泉徴収分を差し引いた金額を計算したい場合は、「譲渡対価(譲渡価額)×89.79%」で算出ができます。
先程の表と同じ譲渡対価(譲渡価額)であれば、源泉徴収分を差し引いた金額は、下記の表の通りとなります。
| 買主の方から 受け取る金額の割合 |
89.79% |
|---|---|
| 譲渡対価が 「100万円」の場合 |
897,900円 (100万円×89.79%) |
| 譲渡対価が 「200万円」の場合 |
1,795,800円 (200万円×89.79%) |
| 譲渡対価が 「300万円」の場合 |
2,693,700円 (300万円×89.79%) |
このような形で算出を行いますので、譲渡対価(譲渡価額)から源泉徴収分を差し引いた金額を求める時も、特に複雑な計算を行う必要はありません。
どちらにしても、源泉徴収をされる金額を知ることができれば、「譲渡対価(譲渡価額)-源泉徴収をされる金額」で求めることができますので、ご自身が計算をしやすいほうを選択してください。
譲渡対価(譲渡価額)につきましては、譲渡対価(譲渡価額)の中に消費税が含まれている場合は、消費税などを含めた金額で計算を行います。
譲渡対価(譲渡価額)と消費税の金額が契約書などで明確に区分をされている場合は、譲渡対価(譲渡価額)の金額のみを源泉徴収の対象として差し支えはありません。
以上が、源泉徴収をされる金額についてとなります。
源泉徴収では、このように算出をした金額を所轄の税務署に納めることになります。
この時、源泉徴収義務者は、売主の方ではありません。
また、納付をする期限も定められておりますので、それまでに支払いを済ませておく必要があります。
いくら、源泉徴収の金額を知ることができても、源泉徴収義務者と納付期限をご存知でなければ、後にトラブルになりかねません。
そういった事態を防ぐためにも、事前に源泉徴収の源泉徴収義務者と納付期限は知っておいたほうが無難です。
そのため、次は源泉徴収を行う際の源泉徴収義務者と納付期限についてご説明致します。
源泉徴収義務者と納付期限
源泉徴収を行う際には、源泉徴収義務者と納付期限が定められており、この決まりに従って納付を行う必要があります。
非居住者の方が不動産を売却する場合の源泉徴収義務者は、買主の方となっております。
また、納付期限は支払った月の翌月の10日までとなっており、これまでに一定の金額を所轄の税務署、又は、最寄りの金融機関に納付しなくてはいけません。
期限内に納付を行わなかった場合は、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがありますので、ご注意ください。
買主の方は源泉徴収義務者ですので、ご自身で納付をする金額を準備するのではなく、売主の方に支払う譲渡対価(譲渡価額)から、納付をする所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。
そして、買主の方は源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を、期限内に所轄の税務署、又は、最寄りの金融機関に納付します。
その際には、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」が必要ですので、こちらを作成した後に納付を行ってください。
納付を行った後は、買主の方から売主の方に「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書」を発行します。
なお、売主の方は、源泉徴収によって一定の金額を減じた譲渡対価(譲渡価額)を受け取りますが、後に確定申告を行うことで、源泉徴収をされた税金が精算をされます。
その際に、源泉徴収をされた税額が、その年の税額よりも多い場合は、差額を還付申告することができます。
源泉徴収では、譲渡対価(譲渡価額)から所得税及び復興特別所得税が差し引かれておりますので、関係があるのはこの2つの税金です。
還付申告をする際には、「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書」などの、支払内容が確認できる書類が必要となります。
以上が、源泉徴収を行う際の源泉徴収義務者と納付期限についてとなります。
源泉徴収を行った後は、期間内に確定申告をして納税を行いますが、その際に気になるのは確定申告の方法と税金の計算方法です。
やはり、非居住者の方の確定申告は、居住者の方とは異なる点があります。
そのため、今度は非居住者の確定申告についてご説明致します。
非居住者の方が不動産を売却する場合の確定申告の方法と、税金の計算方法をご存知でない場合は、併せてご確認ください。
非居住者の確定申告について
非居住者の方が不動産を売却した時には、日本の税務署に確定申告書を提出して、日本の税務署に税金を納付する必要があります。
源泉徴収を行った場合でも、確定申告が必要となりますので、申告を忘れないように注意が必要です。
確定申告をした際に、源泉徴収によって納付をした税額が多ければ、所得税の還付請求も行えます。
それでは、まず確定申告をする際に重要となる、外国人の方や国外の方の税金の計算方法などについてご説明致します。
外国人の方や国外の方の税金
外国人の方や国外への転勤などで非居住者となった方が不動産を売却した場合は、税金をどうやって計算すればいいのか、疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
やはり、課税対象などが居住者の方とは異なるため、税金の計算方法も異なると思われがちですが、実際には居住者の方と同様の方法で税額を計算します。
納付が必要な税額の求め方ですが、まず「譲渡対価(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で譲渡所得の算出を行います。
この時、不動産の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分をされ、譲渡をした年の1月1日において所有期間が「5年」を超えるものは「長期譲渡所得」、「5年」以下のものは「短期譲渡所得」となります。
譲渡所得が算出をできましたら、次は税率を確認していきます。
「長期譲渡所得」の場合は、所得税の税率が「15%」、住民税の税率が「5%」となります。
「短期譲渡所得」の場合は、所得税の税率が「30%」、住民税の税率が「9%」となります。
平成25年から平成49年までは、復興特別所得税も課税をされ、こちらは「各年分の基準所得税額の2.1%」を納付します。
なお、「居住者と非居住者の異なる点」でも申し上げましたように、住民税(所得割+均等割)は、1月1日時点で市区町村に住所がある方が課税をされます。
そのため、非居住者の方で1月1日に住所がない方は、住民税は非課税となります。
ただし、日本国内に事務所、事業所、家屋を所有している場合は、均等割のみ課税をされます。
上記の場合では、不動産の売却を行ったことで、均等割の支払義務が発生をする訳ではありません。
そのため、1月1日時点で市区町村に住所がない場合は、不動産を売却しても、その影響で住民税が課税をされることはありません。
それでは、これらのことを踏まえまして、実際に税金の計算例をご紹介致します。
下記の表に、譲渡所得が「300万円」の場合の各税額をまとめておりますので、参考にしてください。
| 長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 45万円 (300万円×15%) |
90万円 (300万円×30%) |
| 復興特別 所得税 |
9,450円 (45万円×2.1%) |
18,900円 (90万円×2.1%) |
| 住民税 | 15万円 (300万円×5%) |
27万円 (300万円×9%) |
このようにして算出をした税額を申告、納税することになります。
(詳しい不動産売却後の税額の計算方法は、「不動産売却をした際に適用できる特例や税金総額の計算方法 」の記事にあります「譲渡所得税と住民税の税率」の項目をご覧ください。)
納税を忘れてしまった場合は違法となるため、くれぐれも決められた期間内に確定申告をして納税を行ってください。
なお、非居住者の方も居住者の方と同様に、居住用不動産を譲渡した場合の特例(3,000万円の控除)を適用できます。
また、売却をした年の1月1日において、所有期間が「10年」を超える居住用不動産は、更にマイホームを売ったときの軽減税率の特例を適用することも可能です。
この特例を適用した場合、譲渡所得が「6,000万円」以下であれば、所得税の税率は「10%」、住民税の税率は「4%」となります。
譲渡所得が「6,000万円」を超える場合も、「6,000万円」までの部分は上記の税率で計算を行い、残りの部分は通常通り「長期譲渡所得」の税率で計算を行います。
これらの税率をもとに算出をした金額が、納付をする税額となりますので、確定申告の時にはこのように計算を行ってください。
以上が、外国人の方や国外の方の税金の計算方法などについてとなります。
なお、非居住者となった方が、日本で確定申告を行う場合は、納税管理人を定める必要があります。
これは、非居住者の方が日本で確定申告書の提出や納税などを行う時には、納税管理人の方に依頼をする必要があるためです。
毎年、日本で確定申告と納税が必要にならない方でも、日本国内の不動産を売却した時には、日本の税務署に対して確定申告書の提出と納税を行います。
こういった、一時的なものであっても納税管理人の方を選任しなければなりませんので、注意が必要です。
それでは、次は納税管理人を選任して納税を依頼する方法についてご説明致します。
納税管理人を選任して納税を依頼
納税管理人とは、非居住者の方の代わりに、確定申告書の提出や納税などを行う人のことです。
出国後に国内源泉所得が生じる場合は、原則として出国をする前に納税管理人を選任しますが、出国後に必要の都度に選任をすることも可能です。
納税管理人を選任する場合は、非居住者の方の納税地を所轄する税務署長に、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」などの届出を提出します。
届出を提出しましたら、納税管理人のもとに税務署が発送をする書類が送付されるようになります。
(納税管理人の方が非居住者の方の確定申告書などを提出する場合は、こちらも届出の時と同様に、非居住者の方の納税地を所轄する税務署長に提出してください。)
納税管理人は、法人と個人のどちらに依頼をしてもいいのですが、一般的には親族に依頼をすることが多いようです。
税理士の方などが請け負ってくださる場合もありますが、この場合は別途に料金がかかります。
なお、出国をした年の確定申告書の提出期限ですが、これは非居住者の方が出国の時までに納税管理人の届出を提出したかどうかによって異なります。
出国までに選任した場合と出国までに選任しなかった場合の確定申告書の提出期限は、下記の表の通りとなります。
| 条件 | 確定申告が必要な所得 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 出国までに選任した場合 | その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得。 | 翌年2月16日~3月15日 |
| 出国までに選任しなかった場合 | その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得。 | 出国まで |
| 更に、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得。 | 翌年2月16日~3月15日 |
このように、出国までに納税管理人を選任した場合としなかった場合では、確定申告の回数も異なります。
出国前と出国後のどちらにも確定申告を行う場合は、当該申告書において計算された納付すべき税額から、出国前に確定申告(準確定申告)をして納付した税額を差し引いて納税します。
出国前に確定申告をして納付した税額が、当該申告書において計算された納付すべき税額よりも多ければ、その差額を還付申告できます。
また、海外から帰国をするなどして、今後に納税管理人の方に依頼をしなくてもよくなった場合は、解任の届出を行うことで納税管理人を解任することができます。
ですので、帰国をして居住者となった方は、この手続きを行って納税管理人を解任してください。
以上が、納税管理人を選任して納税を依頼する方法についてとなります。
租税条約によって異なる規定がある場合は、そちらに従いますが、主にこのような流れで納税を行うことになります。
今後に非居住者となる可能性があり、居住者である内に不動産を売却して確定申告と納税までを終えたい方は、売却をする時期にお気を付けください。