不動産を売却した際の税金計算時の取得費に計上ができる費用
不動産を売却する際には、様々な金銭の収支を計算しておくことが必要です。
仲介手数料、印紙代、税金の支払いなど、これらの支出についてもある程度予算を立てておく必要があります。
その中でも、税金に関連する部分は、後の売却益に大きく関わる要素だといっても過言ではありません。
不動産を売却した後の税金は、想像以上に高額となってしまうこともあります。
不動産を売却する際には、この税額を少しでも減らせるよう意識をしておくことが大切です。
税額を減らす方法は、特例を適用するなどいくつか方法がありますが、その中でも取得費の計上はとても重要です。
取得費の金額が多くなればなる程、後の税額は少なくなっていきます。
取得費を殆ど計上しなかった場合、余計な税金を支払うことになってしまいます。
そのため、このページでは、不動産を売却した際の取得費の詳細や計上ができる費用についてご説明致します。
まずは、不動産売却における取得費の説明についてです。
目次
不動産売却時の取得費とは?
不動産を売却する際に、よく「取得費」又は「取得価額」などといった言葉を聞くことがあります。
この「取得費」又は「取得価額」とは、どういった費用のことを指すのか具体的に分からないということも珍しくありません。
不動産を売却した際の税金は、当然不動産の売却価格を基に計算をしていきます。
その際には、不動産の売却価格がそのまま「課税譲渡所得」となる訳ではありません。
通常は、不動産を売却した際の「譲渡価額(売却価格)」から、
「取得費(取得価額)」
「譲渡費用(譲渡価額)」
「各種控除(特例など)」
を差し引いた金額となります。
【課税譲渡所得の算式】
課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-各種控除額
課税譲渡所得を減らすためには、「取得費」や「譲渡費用」の金額を増やすことが必須です。
ですから、この取得費について理解し、どういった費用を取得費というのかを知っておくことが大切です。
取得費は、売却した不動産を取得する際に要した費用の合計金額のことを言います。
取得に要した費用に含まれるのは、「不動産の購入価格」だけではありません。
この場合の取得費とは、不動産を購入するために要した費用「全般」が含まれます。
例えば、売却した不動産を取得した際に掛かった、
「仲介手数料」
「印紙代」
「建物の建築請負代金」
なども全て取得費として計上をすることができます。
取得費を計算する際には、「土地部分」と「建物部分」とを分けて金額を計算する必要があります。
取得費として計上ができる経費
取得費には、売却した不動産を取得する際に要した
「建物の購入代金」
「建築代金」
「購入手数料」
「設備費や改良費」
などの経費を計上することができます。
これらの費用がある場合には、余さず取得費に加算しておくことが大切です。
取得費に加算ができる費用は、上記の費用以外にも多数存在します。
詳しい取得費に計上ができる費用につきましては、お手数をお掛け致しますが、「不動産を売却する際に必要になる各費用の計算方法と合計金額」の記事にあります「取得費として計上できる費用」の項目をご覧ください。
(事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません)
これらの費用を全て取得費として計上することができれば、後の税額を通常よりも少なく抑えることができます。
なお、相続により取得した不動産の場合は、それぞれの費用の計上の際に少々注意が必要となります。
次は、こういった相続により取得した不動産の取得費を計算する際の注意点についてご説明致します。
相続により取得した不動産の場合
相続により取得した不動産は、取得費を計算する際に少々注意が必要となります。
相続不動産の場合、その不動産を取得したのは相続人ではなく、「被相続人」です。
そのため、取得費を計算する際には、現在の価格で価値を割り出すのではなく、「被相続人」の方が支払った当時の金額を引き継いでの計算をしなくてはいけません。
(相続財産を取得した際の相続税額にしては、現在の価値で計算をするのが一般的です)
相続税は、相続財産の価値が高ければ高い程高額となります。
相続税を支払った不動産をその後に売却した場合、二重で譲渡税の納付も必要となってしまいます。
相続税を支払った上に譲渡税まで必要となると、その税額は高額となるケースも少なくありません。
こういった税金の負担を減らすためには、相続財産を売却した際に適用ができる特例に関して意識をしておくことが大切です。
詳しい
「相続財産を取得した際の取得費に関する説明」と、
「適用ができる特例の説明」
につきましては、お手数をお掛け致しますが、「相続不動産を売却する際の取得費の特例と2種類の税金計算」のページをご覧ください。
取得費に費用を計上する際の証明
売却した不動産の取得費を証明するためには、それ相応の書類などの準備が必要となります。
それぞれの費用に対して証明ができなければ、その金額が不正であっても判断をすることができません。
これでは、税金の申告の際に、税額を改ざんすることが可能となってしまいます。
こういった不正を防ぐためにも、取得費に計上をした金額に関しては、その証明が必要となります。
各費用を証明する書類としては、不動産を購入した際の「売買契約書」や「領収書」などが必要です。
これは、国税庁の「譲渡所得申告のチェックシート(平成28年分用)」にも記載があります。
不動産を購入した際に負担して測量費や、改良費などを取得費に計上する際にも、その際に受け取った契約書や領収書などの書類が必要です。
(契約書や領収書などが無い場合の証明方法につきましては、同ページ内の「契約書がない場合の7つの証明方法」の項目をご覧ください)
これらの書類の準備をした後は、実際に各費用から取得費を計算していきます。
取得費を計算する際には、
「計上できる費用が明らかである場合」と、
「計上できる費用が不明である場合」
でその計算方法が異なります。
次は、それぞれの場合の取得費の計算方法についてご説明致します。
2種類の取得費の計算方法
取得費を計算する際には、当時の不動産の価格を判別できない場合もあります。
不動産の取得費が不明である場合、その費用は取得費に計上できないのが通常です。
これでは、取得費を実額で計算することができません。
取得費の計算ができないということは、後の税額が多くなってしまうことに直結します。
ここで、少しでも税額を減らすためには、何かしろの方法で取得費を計算していかなくてはなりません。
取得費を計算する際には、こういった
「取得費が明らかである場合」と
「取得費が不明である場合」
に応じて2種類の計算方法を選択することができます。
ご自身の状況を整理し、適切なほうの計算方法で取得費を計算することが大切です。
まずは、「取得費が明らかである場合」の取得費の計算方法についてご説明致します。
計上できる費用が明らかである場合
取得費へ計上できる費用が明らかである場合には、「実額取得費」を使用します。
実額取得費では、それぞれ取得費となる費用を実額で合計していきます。
取得費が明らかである場合、この方法で計算をしたほうが最終的な金額が高額になる場合が殆どです。
(かなり昔から代々相続を続けている不動産などは例外となることもあります)
計算の際には、不動産の購入価格以外にも、取得に要した費用と認められるものなら何でも計上をすることができます。
【実額取得費の計算例】
下記の条件の土地を売却した場合の取得費は、次のようになります。
- 当時に購入した際の価格
- 30,000,000円
- 当時に取得のために要した仲介費用
- 1,036,800円
- 当時に取得の際に負担した測量費
- 300,000万円
30,000,000円+1,036,800円+300,000万円=31,336,800円
実額取得費として取得費を計算する際に注意をしておきたいのは、建物の取得価額に対して「減価償却」を行わなくてはならないという点です。
建物は、建築当初から時間が経つにつれ、その価値が下がっていきます。
その下がった価値分を建物の取得価額から差し引いたものが、現在の建物の取得費となります。
建物の減価償却相当額の計算方法につきましては、お手数をお掛け致しますが、「不動産を売却した時に売却益の計算に必要になる減価償却」の記事にあります「建物の減価償却費の償却方法」の項目をご覧ください。
次は、不動産の当時の購入価格などが不明である場合の取得費の計算方法についてご説明致します。
計上できる費用が不明である場合
取得費が不明である不動産を売却した際には、「概算取得費」を使用します。
概算取得費では、その名の通り、「概算」で取得費を計算していきます。
実際に取得費となる金額は、「不動産の売却価格の5%」です。
概算取得費と実額取得費は、それぞれ「土地部分」と「建物部分」とで別々に選択をすることも可能です。
「土地」の購入価額は分かっているけれど、「建物」の取得価額が分からないといった場合などには、
「土地」の取得費は「実額取得費」
「建物」の取得費は「概算取得費」
を使用するといった方法を取ることもできます。
【概算取得費の計算例】
下記の条件の土地を売却した場合の取得費は、次のようになります。
- 土地の取得費
- 2,000万円
- 不動産の売却価格
-
- 土地
- 2,000万円
- 建物
- 1,000万円
2,000万円+(1,000万円×5%)=2,050万円
上記のうち、土地部分も概算取得費であれば、取得費は「150万円」です。
概算取得費では、その金額が実額取得費よりも低くなってしまう場合が殆どです。
概算取得費を使用するケースは、取得費の金額が不明である場合だけとは限りません。
取得費に費用を計上するためには、原則、契約書や領収書などが必要であることは既に記載しました。
取得費を証明できる書類などが無い場合などは、実額取得費ではなく概算取得費を選択することとなります。
しかし、しかるべき手順を踏めば、契約書や領収書などがない費用を取得費として計上することができたというケースも存在します。
取得費の証明となる契約書や領収書などが無い場合には、そういった対策を試してみることも重要です。
契約書がない場合の7つの証明方法
不動産を取得した際の契約書や領収書などを紛失してしまった場合、それらの費用は取得費とできないのが原則です。
契約書や領収書などがない状態で、取得費に各種費用を計上するためには、それ相応の証明となるその他の書類や事柄などが必要となります。
その際の立証方法としては大まかに次のようになります。
- 「市街地価格指数」を用いて土地の購入価格を推定する
- 「建物の標準的な建築価額表」を用いて建物の購入価額を推定する
- 通帳などの出金状況で当時の購入価格を推定する
- 住宅ローンの支払い状況で当時の購入価格を推定する
- 住宅ローンの金額を証明する書類で当時の購入価格を推定する
- 全部事項証明書の抵当権の設定で当時の購入価格を推定する
- 購入当時の価格が記載されている物などで当時の価格を推定する
これらのいずれかの方法で費用の正当性が認められれば、契約書などが無くても各費用を取得費として計上できる場合があります。
更に、上記の証明に加え、
「購入当時の取得の経緯」、
「事情」、
「推定価格」
などを記載した書面(上申書や申述書など)を、確定申告書の付属書類として提出すれば、信憑性が増し承認されやすくなります。
上記の7つの証明方法に関する詳しい説明につきましては、下記で1つずつ説明していきます。
まずは、「市街地価格指数」や「建物の標準的な建築価額表」を用いて各費用を計算する方法です。
市街地価格指数を用いた方法
「市街地価格指数」とは、一般財団法人日本不動産研究所が、全国223都市内の調査地点の地価を年2回調査し、その結果をもとに割り出した地価の指数のことです。
国税不服審判所の過去の裁決事例(平成12年11月16日)では、
「建物の取得価額を着工建築物構造別単価から算定し、土地については市地価格指数を基に算定する方法」
に関して合理的であるとの見解を示しています。
市街地価格指数は、「一般財団法人日本不動産研究所」のホームページから、一部を閲覧することができます。
(ページへ行き、上部の「レポート/刊行物」から「公表資料」をクリック又はページ中部の「公表資料」の中にある「基礎調査」をクリック)
詳しい市街地価格指数をご覧になりたい場合には、刊行物の購入が必要です。
(詳しい資料が必要ない場合には、「無料会員登録」をするだけで閲覧ができます)
市街地価格指数から土地の取得費を計算することで、取得費が不明でも「概算取得費」ではなく「実額取得費」とすることができる可能性があります。
(必ずしも承認されるとは限りません)
公表されている指数は、平成12年3月を基準(100)とし、毎年3月と9月に発表されます。
市街地価格指数を用いた土地の取得費の計算方法は次のようになります。
【市街地価格指数を用いた土地の取得費の算式】
譲渡(売却)金額×取得(購入)時の指数 ÷譲渡(売却)時の指数
上記の算式を基に、
「概算取得費を用いて税額を計算した場合」と
「市街地価格指数から土地の取得費の推定をした場合」
で、実際に取得費を計算してみます。
【売却した不動産の条件】
- 譲渡した土地が存在する場所
- 東京区部
- 土地の種類
- 住宅地
- 土地の譲渡(売却)価格
- 3,000万円
- 土地の取得(購入)時期
- 昭和60年3月
- 市街地価格指数
- 「83.2」
- 土地の譲渡(売却)時期
- 平成20年3月
- 市街地価格指数
- 「88.3」
【取得費の計算例】
- 「概算取得費」を用いて税額を計算する場合
- 3,000万円×5%=150万円
- 「市街地価格指数」を用いて税額を計算する場合
- 3,000万円×83.2 ÷88.3=約28,267,270円→約2,826万円
上記の例では、取得費の金額が「約2,676万円」違うということになります。
建物の標準的な建築価額表を用いた方法
建物の取得費が不明である場合には、「建物の標準的な建築価額」表を用いて当時の購入価格を推定することができます。
建物の標準的な建築価額表とは、
「建築統計年報(国土交通省)」 の 「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表を基に、1m²当たりの工事費予定額を算出(工事費予 定額÷床面積の合計)した数値のことです。
「市街地価格指数」での土地の推定価格と、「建物の標準的な建築価額表」での建物の推定価格を合計すれば、当時購入した不動産の大まかな価格を知ることができます。
建物の標準的な建築価額表と、その数値を用いた建物の取得費の計算方法につきましては、お手数をお掛け致しますが、「不動産売却の際に確定申告が必要になる状況と各種申請方法」の記事にあります「購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合」の項目をご覧ください。
これにより算出した金額が、建物の取得価額ということになります。
建物の標準的な建築価額表を用いて計算をした金額も、必ずしも当時の購入価額を証明するものではありません。
状況や場合によっては、その価格が不適切であるとみなされることもあります。
そのため、事前に税理士や専門家に相談をしてから取得費の計算を行うようにすることが大切です。
不動産の取得費を証明する方法はこれだけではありません。
他にも、不動産の購入時に支払った購入金額を明らかに証明できる通帳などがあれば、取得費としてその費用を計上できる可能性があります。
次は、こういった通帳などの出金状況を確認して、取得費を証明する方法についてご説明致します。
通帳などの出金状況を確認する方法
不動産の取得価額が不明である場合には、何かしろの方法で金額を調べなくては後の税額が高くなってしまいます。
不動産を購入する際には、高額な金銭が動くこともあり、多くの方が銀行振り込みなどの方法で不動産を購入します。
銀行振り込みなどで買主の方に購入代金を支払った場合、その記録は該当の預金通帳に記載されるのが一般的です。
その通帳の入出金履歴には、振り込み先の情報などが簡易的に表示されていることも少なくありません。
これを見れば、不動産を取得した際に支払ったおおよその金額を知ることができます。
当時の預金通帳がない場合には、銀行が保管している預金の入出金の記録(取引履歴)を、有料でプリントアウト(明細書の形式)して貰うことも可能です。
(大体10年位前までのデータならプリントして貰える場合が多いようですので、一度対応する金融期間にご相談ください)
ここまではっきりとした証明があれば、この金額を取得費とすることができる可能性があります。
(預金通帳の入出金履歴で、確実に取得価額が証明できる訳ではありません)
その際に、建物と土地の購入価格が分かれていない場合には、
同ページの「土地と建物の価格を区分する6つの方法」の項目に記載をした方法を用いて、それぞれの取得価額を計算してください。
それぞれの取得価額の算出が終われば、後は確定申告の際に、先程準備をした証明のコピーなどを添付するだけです。
当時に使用した預金通帳が無く、銀行にも入出金の記録(取引履歴)がない場合には、当時に組んだ住宅ローンの情報から取得費を証明する方法もあります。
次は、当時に組んだ住宅ローンなどの情報を確認して、取得費を証明する方法についてご説明致します。
住宅ローンの支払い状況で確認する方法
不動産を購入する際には、多くの方が住宅ローンなどを借り入れて購入代金を確保します。
その金額は、元手にもよりますが、不動産の購入代金とほぼ同じである場合も少なくありません。
(事前に高額な金額を所有しており、足りず分だけを借り入れた場合などは金額が大幅に異なる可能性があります)
そのため、不動産を購入する際に組んだ住宅ローンの金額を確認することができれば、不動産の購入金額を証明できる可能性があります。
住宅ローンを返済する際には、口座引き落しによって返済を行っていくのが一般的です。
この場合、通帳に住宅ローンを返済するために引き落とされた金額が記載されています。
その金額を確認すれば、不動産を購入するために借り入れた住宅ローンの金額(購入金額)を確認することができます。
通帳に住宅ローンを返済した金額の一部しか記載されていない場合には、その金額と返済プランから大体の金額を割り出すことも可能です。
この場合、取得費として認められるかは、いかに情報に信憑性があるかが鍵となります。
ここで情報の信憑性が認められなければ、これらの金額を取得費として計上することはできません。
なるべく多くの情報を集め、情報に信憑性があるということを提示することが大切です。
なお、住宅ローンの返済履歴以外に住宅ローンの借入金額を証明する術がある場合には、そちらの方法を選択することもできます。
次は、上記以外の方法で、住宅ローンの借入金額を調べる方法についてご説明致します。
住宅ローンの金額を証明する書類で確認する方法
住宅ローンの借入金額は、通帳の入出金履歴以外でも確認をすることができます。
金融機関から住宅ローンの借り入れを行う際には、通常、「金銭消費貸借契約書」などを交わします。
この契約書には、多くの場合、住宅ローンによって借り入れを行う予定の「ローン総額」が記載されております。
借り入れたローンの総額が分かれば、購入した不動産の大まかな購入金額を推定することができます。
「金銭消費貸借契約書」などがない場合には、
- 住宅ローンの償還表
- 住宅ローンの返済明細表
などでもローンの総額を推定することが可能です。
これらの書類を提示する際には、その書類に間違いがないかをよく確認しておくと安心です。
添付した書類に間違いがあった場合、その金額を取得費とすることはできません。
手元にある書類は、本当に当該不動産を購入するために借り入れた住宅ローンのものなのか、十分に確認を行うことが大切です。
上記のような書類が手元に無いという場合には、その他の公的書類を参照にすることで住宅ローンの金額を確認できる場合があります。
次は、公的書類を参照して、住宅ローンの借り入れ金額を確認する方法についてご説明致します。
全部事項証明書の抵当権の設定で確認する方法
不動産を購入する際に住宅ローンを組んだ場合、担保を設定しなくてはならないのが一般的です。
その担保は、購入をした不動産である場合が殆どです。
住宅ローンの返済が困難となった際には、担保となった不動産が差し押さえられます。
そのために必要となるのが、不動産の「抵当権設定」です。
住宅ローンの借入先と借主は、ローンの借り入れを行う際に、この抵当権を設定します。
抵当権の設定をすると、全部事項証明書(登記簿)に、その設定が記録されます。
記録される情報には、借り入れをした住宅ローンの金額も含まれているのが一般的です。
これにより、抵当権の設定を確認すれば、借り入れた住宅ローンの金額を確認することができます。
住宅ローンの金額は、全部事項証明書(登記簿)の「乙区欄」に記載がされております。
具体的には、「権利部(乙区)」の「権利者その他の事項」の中の「債権金額」が、借り入れをして購入に充てた金額です。
全部事項証明書(登記簿)は、法務局で取得できる公的な書類ですので、準備ができれば不正な情報とみなされる可能性も少なくなります。
全部事項証明書(登記簿)の抵当権設定を提示する際には、購入した不動産の
「所有権移転の日」と
「抵当権設定の日」
が一致するがどうか、
「それが本当に不動産を購入するために設定した抵当権なのかどうか」
などを確認しておくと、取得費として認められる可能性を更に高めることができます。
全部事項証明書(登記簿)の取得が面倒である場合や何かしろの理由で金額の確認ができない場合には、
全部事項証明書(登記簿)以外で、不動産の取得費を確認する必要があります。
不動産の購入価格は、本当に当時のものだという証明が取れれば、公的な書類以外でも証明とすることができる場合があります。
次は、こういった購入当時の価格が分かる物で取得費を証明する方法についてご説明致します。
購入当時の価格が分かる物で確認する方法
不動産を購入した際に、住宅ローンを組まなかった場合などには、住宅ローンの情報によって取得費を推定することはできません。
こういった場合には、購入当時の価格を住宅ローンの記録以外で探す必要が出てきます。
購入当時の価格を調べる方法としては、既に
「市街地価格指数」や
「建物の標準的な建築価額表」
を用いる計算を記載しました。
これらの方法以外に、当時の購入価格を推定する方法はいくつか存在します。
購入当時の価格が分かる具体的な物として、「購入当時の不動産のパンフレット」などが挙げられます。
パンフレットがない場合でも、当時に不動産を購入した際の仲介業者が、当時の購入価格に関して確認できる書類(契約書など)を持っている可能性もあります。
不動産会社や仲介業者に直接事情を説明し、当時の契約書などを再発行して貰えば、その書類を取得費の証明とすることも可能です。
(書類によっては手数料などが発生する可能性があります)
「売買契約書」の再発行を行うための手順は下記のようになります。
【売買契約書を再発行する手順】
- 当時の売主の方に契約書の内容が同じであることを確認して貰う
- 当時契約をした仲介業者にも契約内容の確認をして貰う(仲介依頼をしてない場合は不要)
- 当時の売主の方と仲介業者の署名・押印を貰う
- 売買契約書の再発行が行われる
- 再度、収入印紙を契約書へ貼り付ける
収入印紙の再貼付が気になる方は、当時の売主の方に直接売買契約書のコピーを貰うという手もあります。
売主の方の連絡先が不明である場合や関係が悪い場合などには、仲介業者を通して書類の再発行を行うのが無難です。
以上が、取得費を計上する際に契約書や領収書がない場合の証明方法になります。
土地と建物の価格を区分する6つの方法
不動産を売却する際には、土地と建物を同時に売却することも珍しくありません。
土地と建物を同時に売却した場合、前述のように土地部分と建物部分の取得費を分けて計算する必要があります。
当時に土地と建物の購入価格が区分された状態で購入していれば、取得費へそのまま計上することができます。
購入当時に土地と建物を一括で購入した場合には、それぞれの価格が区分されていない場合もあります。
土地と建物の価格が区分されていない場合には、適切な方法でそれぞれの価格を区分することが必要です。
土地と建物の購入価格の区分の方法に関しては、主に下記の6つの方法があります。
- 建物の購入時の時価(建物の標準的な建築価額)で按分する
- 土地購入時の時価(公示地価・基準地価・路線価など)で按分する
- 土地と建物の購入時の時価の比で按分する
- 土地と建物の固定資産税評価額の比で按分する
- 契約書などに不動産購入時の消費税額が記載されている場合にはその金額で按分する
- 不動産鑑定士に依頼し按分する
それぞれの取得費の計算方法につきましては、下記で詳しくご説明致します。
建物の標準的な建築価額で按分する方法
土地と建物を一括購入し、その合計金額が分かっている状態であれば、それぞれの推定価格を割り出し按分することが可能です。
その際には、どちらか一方の時価さえ分かれば、後は分かっている合計金額からその金額を差し引くことで片方の価格も算出をすることができます。
今回は先に建物の価格を算出し、その後に土地の価格を算出する方法についてご説明致します。
建物の当時の購入価格は、前述の「建物の標準的な建築価額表」を基に算出をすることが可能です。
「建物の標準的な建築価額表」によりそれぞれの購入価額を計算する方法につきましては、お手数をお掛け致しますが、「不動産売却の際に確定申告が必要になる状況と各種申請方法」の記事にあります「購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合」の項目をご覧ください。
一括で購入した土地と建物の価格を按分する際には、先に土地の価格を計算しても問題はありません。
次は、先に当時の土地の価格を計算した上で、土地と建物の価格を按分する方法についてご説明致します。
公示地価などから按分する方法
土地の時価を算出する方法としては、「公示地価」「路線価」「基準地価」を用いる方法があります。
【公示地価・路線価・基準地価の違い】
- 公示地価
- 公示地価とは、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格のことです。
- 価格の基準日は、その年の1月1日時点で、毎年3月中旬頃に発表されます。
- 公示地価の他に、「地価公示」「地価公示価格」「公示価格」「標準価格」「標準地価格」などと表記されることもあります。
- 標準地・基準地検索システム
- 路線価
- 路線価とは、一定の距離をもった「路線」に対して決められた路線価格のことです。
- 「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、一般的には「相続税路線価」を指す場合が多いです。
- 路線価(相続税路線価)は、公示地価の8割程度が目安です。
- 路線価図・評価倍率表
- 基準地価
- 基準地価とは、都道府県が調査し公示する標準値の価格のことです。
- 公示地価とほぼ同様ですが、価格の基準日が7月1日であり、毎年9月20日頃に公表されます。
- 標準地・基準地検索システム
(売却した)不動産を購入した時期の公示地価・基準地価を調べると、1m²当たりの土地単価が分かりますので、その数値と売却した土地の面積を掛けます。
【土地の時価を求める算式】
不動産購入当時の公示地価(基準地価)×売却した土地面積=当時の土地の購入価格(推定)
上記以外にも、路線価と公示地価(基準地価)を用いた計算方法もあります。
路線価と公示地価(基準地価)を用いた計算方法につきましては、お手数をお掛け致しますが、「所有している不動産を売却する際に知っておきたい基礎知識」の記事にあります「土地の公示地価の算出方法」の項目をご覧ください。
これら方法は決して正確な購入価格を算出する訳ではありませんので、時には価格に誤差が出る可能性もあります。
時価による按分が上手くいかない場合には、専門のプロへの相談も視野に入れておくことが大切です。
当時の時価の比で按分する方法
先程は、土地と建物の時価を算出し、その金額を基にそれぞれの取得費を算出しました。
今回の方法では、建物と土地の時価の比を用いて当時の価格を推定します。
まず、前述の方法などで建物と土地の当時の時価を計算し、その金額からそれぞれの価格の比を割り出します。
【計算例】
建物の当時の時価が「1,500万円」
土地の当時の時価が「3,000万円」
上記のような場合の建物と土地の時価の比は下記のようになります。
1(建物):2(土地)
この比を、契約書や領収書などで残っている不動産の購入価格に当てはめます。
【計算例】
契約書に記載があった購入金額の総額が「3,000万円」であった場合
上記の条件の建物と土地の当時の推定価格は下記のようになります。
「3,000万円」のうち、1(建物):2(土地)の比率となるように合計金額を分けるため、
建物の取得費が「1,000万円」
土地の取得費が「2,000万円」
となります。
この例ではそれぞれの比がそれ程複雑ではないため、このように簡単に価格の比を出すことができました。
土地と建物の価格の比が複雑になりそうな場合には、この方法では計算が上手くいかない場合もあります。
土地と建物の価格の比が複雑である場合の価格の比の算出方法につきましては、下記の「固定資産税評価額で按分する方法」の項目で詳しくご説明致します
下記の価格の按分方法は、「固定資産税評価額」を用いた計算方法ですが、
固定資産税の部分を時価に置き換えれば同じように計算をすることが可能です。
固定資産税評価額で按分する方法
一括で購入した土地と建物は、それぞれの「固定資産税評価額」の比で価格を按分する方法もあります。
固定資産税評価額により価格を按分する際には、主に2種類の計算方法があります。
1つは固定資産税から建物の大まかな価格を算出し、その後に当時の購入金額の総額からその金額を差し引いて、それぞれの価格を算出する方法です。
【1つ目の方法の算式】
「建物の取得費の算出」
当時の購入金額の総額×建物の固定資産税評価額/(建物の固定資産税評価額+土地の固定資産税評価額)
「土地の取得費の算出」
購入金額の総額-建物の取得費
【取得費の計算例】
下記の条件の不動産を売却した場合の取得費は、次のようになります。
- 当時の購入金額の総額
- 3,000万円
- 建物の固定資産税評価額
- 700万円
- 土地の固定資産税評価額
- 1,400万円
「建物の取得費の算出」
3,000万円×700万円/(700万円+1,400万円)=1,000万円
「土地の取得費の算出」
3,000万円-1,000万円=2,000万円
上記の計算から、この場合の取得費は
建物が「1,000万円」
土地が「2,000万円」
ということになります。
もう1つの方法は前述の時価の比で按分する方法と同じように、それぞれの比を計算して按分を行います。
計算を行う際には、建物部分に消費税が掛かるということを視野に入れて価格を算出します。
【2つ目の方法の算式(連立方程式)】
土地A+建物(B×1.08)=当時の購入価格の総額
土地A:建物B=土地の固定資産税評価額:建物の固定資産税評価額
(少数点以下は、四捨五入)
【取得費の計算例】
下記の条件の不動産を売却した場合の取得費は、次のようになります。
- 当時の購入金額の総額
- 3,000万円
- 建物の固定資産税評価額
- 700万円
- 土地の固定資産税評価額
- 1,400万円
土地A+建物(B×1.08)=3,000万円
土地A:建物B=1,400万円:700万円
上記の計算から、この場合の取得費は
建物が「約9,740,260円」
土地が「約20,259,740円」
ということになります。
建物の消費税を視野に入れて計算を行っているため、1つ目の方法とは答えが異なっております。
これらの方法で取得費の計算を行う場合には、ご自身の状況に合っているほうで計算を行うことが大切です。
購入時の消費税額で按分する方法
土地と建物を一括で購入した際の契約書や領収書などには、その際に掛かった消費税額などが記載されていることがあります。
購入当時の消費税額が分かる場合、それを基に土地と建物の価格を按分することが可能です。
不動産を売買すると、その金額に見合った消費税の支払いが必要ですが、それは建物部分だけとなります。
土地部分には、基本的に消費税は掛からないため、記載されている消費税額は全て建物の購入価格に対して課税がされています。
建物の購入価格のみに課税がされているということは、その金額から建物の価格を割り出せるということです。
消費税額から、当時の建物の購入価格を算出する方法につきましては、お手数をお掛け致しますが、「不動産売却の際に確定申告が必要になる状況と各種申請方法」の記事にあります【建物の取得価額の計算方法】の項目をご覧ください。
この方法で建物の購入価格を算出すれば、後は土地部分の購入価格も簡単に算出を行うことができます。
【算式】
購入価格の総額-建物部分の価格=土地部分の価格
こうして算出された価格が、当時購入した建物と土地の価格ということになります。
契約書や領収書などに消費税額の記載がない場合には、この方法で価格を算出することはできません。
不動産鑑定士に依頼し按分する方法
前述の方法でどうしても不動産の価格を按分できない場合には、不動産鑑定士に価格の按分を依頼することもできます。
不動産鑑定士に価格の按分を依頼すれば、価格が不正だと判断される可能性も減り、後のトラブルも回避しやすくなります。
判別が難しい事柄も、不動産鑑定士ならば適切に不動産の価格を按分してくださいます。
不動産鑑定士に不動産の価格の按分を依頼した際のデメリットとしては、それ相応の報酬が必要となってしまうという点です。
不動産の価格の按分に関する報酬は、
「依頼する不動産鑑定士」や
「鑑定する状況」
などによって金額が変わってきます。
適正な報酬に関しては、実際に不動産鑑定士に聞いてみなくては分かりません。
実際に不動産を鑑定する前に、鑑定後の報酬について話を聞いておくと、後の報酬について目安を立てやすくなります。
なるべく必要経費を抑えたいという方は、ご自身で不動産の価格の按分を行うことが必要です。
(ご自身で価格の按分を行うことができない場合には、少々出費があってもトラブル対策として不動産鑑定士に依頼をするのが無難です)
贈与により取得した不動産の取得費
不動産を取得する際の取得方法は、購入以外にも様々なものがあります。
時には、不動産を誰かから贈与され、取得するということもあります。
不動産の贈与とは、簡単に言うと、他人から無償で土地や建物などの不動産を貰うことです。
こう聞くと相続と似ている印象を覚えるかもしれませんが、正式には贈与と相続の概念は異なっております。
相続では、被相続人が亡くなった時点で、自動的に相続人に財産が移ります。
贈与では、贈与者(贈与する側)が生きている内に、受贈者(受け取る側)に財産を贈与します。
(贈与者が「贈与」の意思表示をし、受贈者が「貰う」という意思表示をすることで成立します)
不動産を贈与により取得し売却した場合、相続不動産同様に、少々特殊な取得費の計算が必要となってしまうのが一般的です。
これは、個人から贈与されたのか、法人から贈与されたのかでも計算の方法が異なってきます。
贈与により取得した不動産を売却する際には、状況に合った方法で取得費を計算することが大切です。
個人から贈与された不動産の場合
個人からの贈与により取得した不動産を売却する場合、その取得費の算出方法は通常時とは異なる可能性があります。
不動産を贈与されたということは、その不動産を購入したのは受贈者ではなく贈与者です。
これは、相続により取得した不動産を売却した場合と同じ状況です。
相続により取得した不動産を売却した際には、被相続人が不動産を取得した際の価格などを受け継ぐということは既に記載をしました。
贈与により取得した不動産も、これと同様で、贈与者が不動産を取得した際の各費用を引き継いで取得費を計算しなくてはなりません(生前贈与も同様)。
現在の価値が、その当時よりも高かったとしても、不動産の取得費は当時のままで計算を行います。
【取得費の計算例】
Aさんが過去に「3,000万円」で購入した不動産をBさんに無償で贈与し、Bさんがそれを売却した場合
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
今回の例では、不動産を当時に購入した「Aさん」の取得費を引き継ぐこととなりますので、「3,000万円」が取得費となります。
購入価格の取得費以外に関しましては、現在の代金を取得費とすることができます。
【当時からの引継ぎが必要ない費用の一例】
- 贈与を受ける際に行った所有権移転登記の費用や登録免許税など
- 贈与を受ける際に行った測量費
- 贈与を受ける際に行った工事費
これらの費用と、引継ぎが必要な費用を整理し、取得費を計算するようにしてください。
法人から贈与された不動産の場合
不動産の贈与は、贈与者が必ず個人であるとは限りません。
時には、法人から個人へ不動産の贈与が行われることもあります。
法人から不動産の贈与が行われた場合も、受贈者が不動産の購入していないということに変わりはありません。
こう考えると、法人から不動産が贈与された場合でも、個人からの贈与と同じように贈与者の取得費を受け継ぐ必要があるように感じるかもしれません。
しかし、贈与者である法人には、個人の場合と異なり、キャピタルゲイン課税(時価課税)が行われます。
(相続や個人からの贈与で何かしろの財産を取得した場合、被相続人や贈与者に対しての課税は繰り延べられます)
贈与者である法人側にも課税がされるということは、通常の不動産の売買時と同じ状況ということになります。
そのため、法人から不動産の贈与を受けた際には、その取得費は受贈者へ引き継がれなくなるのが普通です。
この場合の取得費は、受贈者が贈与を受けた際の「時価」となる場合が殆どです。
【取得費の計算例】
法人Aが過去に「3,000万円」で購入した不動産をBさんに無償で贈与し、Bさんがその不動産を売却した場合
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
今回の例では、法人Aにキャピタルゲイン課税がされることとなりますので、取得費は引き継がずに時価の「3,300万円」が取得費となります。
法人から贈与された不動産を売却する際には、こういったことに注意をして取得費を計算することが重要です。
低額譲受により取得した不動産
不動産を贈与ではなく、購入した場合には、その際の購入価格などが取得費となります。
ここで問題となるのは、その不動産を時価ではなく、時価よりも著しく低い価格で購入していた「低額譲受」の場合です。
(低額譲渡は不動産を低額で「譲渡する」こと、低額譲受は不動産を低額で「譲渡される」ことです)
例:
「Aさんの親が所有している時価が「3,000万円」の土地を、Aさんに「1,000万円」で譲渡した場合など」
低額譲受の概念については、よく時価の「1/2未満の価格」などと言われておりますが、これは法人に不動産を売却した際の基準になります。
個人から個人へ不動産を譲渡した場合には、「著しく低い価額」の基準は設けられておりません。
不動産を購入した際の価格が「著しく低い価額」であったかどうかは、社会通念により判断をすることになります。
不動産を低額譲受により取得した際には、その後の取得費の計算に関して少々注意が必要です。
低額譲受により取得した不動産は、
「当時の売主が個人であったか法人であったか」
「売主が個人であった場合には、現在の譲渡が黒字であったのか赤字であったのか」
でも取得費の計算方法が変わってくるのが一般的です。
現在売却を考えている不動産が、低額譲受により取得したものである場合には、一度、取得費の金額について整理しておくことが大切です。
事前に確認をした上で、後の取得費を計算しておけば、確定申告などもスムーズに行いやすくなります。
個人から低額譲渡された場合
個人から不動産を低額譲渡された際には、取得費の計算が通常時とは異なる可能性があります。
低額譲受時は、主に下記のような状況に分けられます。
- 低額譲受時の価額が時価の1/2以上
-
- 低額譲渡をした側の譲渡益が「黒字」
- 低額譲渡をした側の譲渡益が「赤字」
- 低額譲受時の価額が時価の1/2未満
-
- 低額譲渡をした側の譲渡益が「黒字」
- 低額譲渡をした側の譲渡益が「赤字」
上記の内、「赤い字」で記載がされた「2.2」の条件以外では、「低額譲受時の購入価格」が取得費となります。
「赤い字」で記載がされた「2.2」の条件の場合には、「当時の持ち主の取得費」を引き継いで取得費を計算します。
それぞれの取得費の計算例につきましては下記のようになります。
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
【「2.2」の条件以外の場合の取得費の計算例】
Aさんが過去に「3,000万円」で購入した不動産をBさんが「1,000万円」で低額譲受した場合
今回は、Aさんに譲渡益(100万円)が発生しておりますので、取得費は引き継がずに低額譲受時の購入価格である「1,000万円」が取得費となります。
【「2-2」の条件の場合の取得費の計算例】
Aさんが過去に「3,000万円」で購入した不動産をBさんが「1,000万円」で譲渡譲受した場合
今回は、Aさんに譲渡損失(△2,000万円)が発生しておりますので、取得費はAさんのものを引き継ぎ「3,000万円」となります。
低額譲渡により取得した不動産を売却する際には、まず状況を整理し、適切な方法で取得費を計算するようご注意ください。
法人から低額譲渡された場合
不動産を低額譲渡された際に、その相手が法人であった場合、個人の場合とは異なる方法で取得費の計算を行う必要があります。
法人から不動産を低額譲渡された際には、譲渡時点で法人に対して課税(時価で計算)がされるのが一般的です。
時価による課税が行われたということは、他の事例と同様に、取得費の引き継ぎは行われないということになります。
そのため、法人から低額譲渡された不動産の取得費は、その譲渡時点の「時価」となるのが一般的です。
【取得費の計算例】
法人Aが過去に「3,000万円」で購入した不動産をBさんに低額譲渡(その時点の時価は「3.300万円」)し、Bさんがそれを売却した場合
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
今回の例では、不動産を当時に購入した「法人A」の取得費は引き継がないため、低額譲渡時点の不動産の時価「3,300万円」が取得費となります。
法人から取得した不動産は、基本的に「みなし譲渡」となるため、取得費を引き継ぐケースは殆どありません。
不動産を負担付贈与された場合
不動産などの贈与の際には、通常の贈与以外にも「負担付贈与」という方法を取ることもできます。
負担付贈与とは、財産の受贈者に借金などの一定の債務を負担させることを条件に財産の贈与を行うことです。
その際の債務金額は、通常、「負担額」などと呼ばれます。
負担付贈与時の取得費は、大体「低額譲渡」の場合と同じ計算方法となります。
違う点といえば、低額譲受時の「購入価格」を「負担額」に置き換えて計算をするという点です。
個人から不動産を「低額譲渡」された場合には、前述の通り、当時の売主からの購入価格を引き継ぎ取得費の計算を行います。
法人から不動産を「低額譲受」された場合には、その当時の購入価格が取得費となります。
負担付贈与により不動産を取得した際には、これらの購入価格を「負担額」に置き換えます。
【取得費の計算例】
法人Aが過去に「3,000万円」で購入し、まだ債務(負担額)が「1,000万円」残っている不動産をBさんに負担付贈与により取得した場合(その時点の時価は「3,300万円」)
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
今回の例では、不動産を当時に購入した「法人A」の取得費は引き継がず、当時の負担額である「1,000万円」が取得費となります。
(個人からの負担付贈与であれば、以前の持ち主からの取得費を引き継ぐため取得費は「3,000万円」となります)
これで不動産を贈与や低額譲渡などにより取得した場合の取得費の計算方法の説明は終わりです。
借地権を譲渡した場合の取得費
土地には、借地権というものがあり、これは他人から土地を借りている状態のことを指します。
土地を借りているということは、その土地を売却した場合の取得費の計算がどうなるのか疑問に感じてしまかもしれません。
借地権を譲渡した際の取得費の計算方法は、その状況などによって計算方法が異なります。
借地権を譲渡する際の状況としては、主に下記のようなものが想像できます。
- 借地人が借地権を譲渡する
- 地主が借地権を取得し譲渡する
- 借地人が底地を取得し譲渡する
- 借地権付き建物を譲渡する
- 地主と借地人で土地を譲渡する
- 借地権の概算取得費を計算する
これらの状況下では、それぞれで取得費の計算方法が異なる場合があります。
借地権の譲渡を行う際には、ご自身が置かれている状況を整理し、それに対応した方法で取得費を計算することが大切です。
それぞれの状況下での取得費の計算方法につきましては、下記でご説明致します。
借地人が借地権を譲渡する場合
借地権の取得費に関しては、主に下記のような費用を取得費として計上することが可能です。
【借地権を譲渡する際に取得費に計上できる費用】
- 地主の方などに支払った借地権の対価
- 権利金
- 借地権の購入代価又は立退料などの金額
など - 借地権である土地上に存在する建物などを取得した際の購入代価の内、借地権の対価※が含まれている場合のその金額(その際の金額が購入対価の10%以下の場合は、借地権の取得費ではなく建物などの取得費に含めることができます)
- 借地部分を改良するために要した費用(構築物の取得費とすることが相当なものについては、建物の取得費に含めることができます)
- 土地の埋め立て
- 地盛り
- 地ならし
- 切土
- 防壁工事などの整地又は土地の改良
- 上下水道工事のために要した費用
など - 借地契約の更新料又は変更(名義書換料など)のために支払った費用
- 借地権上の建物を増改築するにあたり、地主の方などに対して支払った承諾料など
- 借地権と建物などを共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当初からその建物などを取壊して土地を利用する目的であったことが明らかな際の建物などの帳簿価額や取壊し費用(建物取得価額(帳簿価額)+取壊し費用-廃材処分による収入金額)
- 借地権の取得のために要した仲介手数料などの費用
- 法人からの無償譲渡、低額譲渡により借地権を取得した場合には、受贈益として課税された際の「借地権の価額」と「支払った金額」との差額(受贈益金額)
- 借地権取得のために借り入れた借入金利子のうち、借入日から借地権の使用開始日までの期間に対応する部分(事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入している部分を除く)
- 借入れに際して負担した公正証書作成費用
- 抵当権設定登記費用
- 借入担保のために締結した保険料等借入れのために通常必要と認められる費用
など - みなし譲渡課税が行われていた場合の借地権の時価
上記の説明の「代価」とは、借地権や借地権上の建物などを取得する際に要した費用のことになります。
例:購入代価は購入価格と同じ金額です
通常の土地同様、これらを全て合計したものが、借地権の取得費となります。
地主が借地権を取得し譲渡する場合
借地権の譲渡を行う可能性があるのは、借地人だけではありません。
時には、地主が借地人に立ち退きなどをお願いし、借地権を取得した上で底地と共に土地を売却するという場合もあります。
この場合の取得費は、売却した「底地」と「借地」の土地部分を分けて計算を行うのが通常です。
それぞれの取得費の計算方法につきましては、次のようになります。
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
【イ 旧借地権部分に係る取得費】
「旧借地権等の消滅につき支払った対価の額」とは、借地人の方に支払った立退料など、その借地を取得するために要した費用の合計額です。
計算例:
- 旧借地権等の消滅につき支払った対価の額
- 300万円
- 売却した借地であった部分の面積
- 30m²
- 借地であった土地部分の全体面積
- 30m²
上記の条件を算式に当てはめると、取得費は「300万円」となります。
【ロ 旧底地部分に係る取得費】
「譲渡した土地の取得費」とは、当時にその土地を取得する際に要した費用のことです。
計算例:
- 譲渡した土地の取得費
- 300万円
- 借地権の設定時に取得費とされた金額
- 100万円
- 売却した借地であった部分の面積
- 30m²
- 借地であった土地部分の全体面積
- 30m²
上記の条件を算式に当てはめると、取得費は「200万円」となります。
底地と借地権を同時に譲渡する際に、どちらか一方だけの取得費が不明である場合には、一方だけに概算取得費を使用し、もう一方には実額取得費を使用することもできます。
借地人が底地を取得し譲渡する場合
借地権を譲渡する際には、借地人の方が、地主の方から底地を取得した上で譲渡をすることもできます。
この場合も、先程と同様に売却した「底地」と「借地権」の部分に分けて取得費の計算を行う必要があります。
それぞれの取得費の計算方法につきましては、次のようになります。
スマートフォンなどでページを閲覧している方は、下記の画像が見辛い場合があります。
そういった場合には、お手数をお掛け致しますが、画像をクリックすることで拡大された画像を閲覧することができます。
【イ 旧底地部分に係る取得費】
「底地の取得のために要した金頷」とは、その底地を取得するために地主の方などに支払った代価などの合計額です。
計算例:
- 底地の取得のために要した金頷
- 300万円
- 売却した借地であった部分の面積
- 30m²
- 借地であった土地部分の全体面積
- 30m²
上記の条件を算式に当てはめると、取得費は「300万円」となります。
【ロ 旧借地権部分に係る取得費】
「旧借地権等の設定又は取得に要した金額」とは、その借地権を取得するために地主の方などに支払った代価などの合計額です。
計算例:
- 底地の取得のために要した金頷
- 200万円
- 売却した借地であった部分の面積
- 20m²
- 借地であった土地部分の全体面積
- 20m²
上記の条件を算式に当てはめると、取得費は「200万円」となります。
この場合も、一方だけに概算取得費を使用し、もう一方には実額取得費を使用するができます。
借地権付き建物を譲渡する場合
借地権とその土地上の建物を同時に取得した場合などは、借地権付き建物といわれる状態となります。
借地権上に建物があるといっても、その建物まで借物となってしまう訳ではありません。
多くの場合、借地権付き建物を購入すると、その建物自体は所有権を所持できるのが一般的です。
土地は借地、建物は所有権している状況となるため、取得費の計算は借地権と建物で別々に計算を行う必要があります。
借地権の取得費の計算方法は、前述の「借地人が借地権を譲渡する場合」と同様です。
建物部分に関しては、その当時の「時価」が取得費となるのが一般的です。
(建物を取得するために要した「借地権の対価」などは、借地権のほうの取得費となります)
ここで意識しておきたいのは、その費用が購入対価の10%未満である場合には、建物の取得費として計算を行うこともできるという点です。
これだけでは分かりにくいかもしれませんので、実際に下記の例をご覧ください。
【取得費の例】
以前に借地権付き建物を「3,000万円」で購入し、その際の価格の内訳は下記のようになりました。
建物→「2750万円」
借地権→「250万円」
この場合、建物を取得するために取得した借地権の対価が「250万円」であり、購入対価の10%未満です。
このように借地権の対価が購入対価の10%未満の場合には、その金額を建物の取得費とすることもできます。
上記の例では、「3,000万円」全てを建物の取得費とすることができます。
借地権の対価を建物の取得費とした場合、借地権の対価部分の金額にも減価償却が行われますので、
そのことに注意をした上で、借地権の対価を建物の取得費とするかを決めることが大切です。
借地権の概算取得費を計算する場合
借地権の取得費が不明である場合には、通常の不動産と同様に概算取得費を使用できるということは既に記載をしました。
底地と借地権の取得費は、原則別々に計算をする必要があり、これは概算取得費を選択した場合も同様です。
取得費を別々に計算するということは、片方の取得費のみを概算取得費とすることもできるということです。
底地の価格は分かっているけれど、借地権の取得費が不明である場合などには、
底地を「実額取得費」で計算し、
借地権を「概算取得費」で
計算することも可能です。
借地権の概算取得費は、単純に売却価格の5%とはなりません。
借地権の概算取得費を計算する際には、借地権割合も売却価格に乗じておく必要があります。
【借地権の概算取得費の算式】
売却価格×借地権割合×5%=借地権の概算取得費
借地権の売却価格が「3,000万円」、その借地権の借地権割が「60%」であれば概算取得費は下記のようになります。
【概算取得費の計算例】
3,000万円×60%×5%=90万円
今回の例では、借地権の概算取得費は「90万円」ということになります。
通常通り取得費を計算した場合には「150万円」が取得費となるため、通常時よりも金額が下がってしまうということを想定しておくことが大切です。
借地権の取得費が不明である場合には仕方がありませんが、取得費が実額で分かる場合には選択するケースはそれ程ないかもしれません。
底地の概算取得費を計算する場合
借地権の概算取得費を計算する際には、売却価格に借地権割合を乗じた上で5%を乗じる必要がありました。
底地の概算取得費を計算する際にも、通常の概算取得費の計算とは少々異なる計算を行わなくてはなりません。
底地の概算取得費を計算するためには、まずその底地が更地であった場合の「時価」を調べる必要があります。
時価が分かりましたら、下記の算式を用いて、概算取得費を計算します。
【底地の概算取得費を計算するための算式】
土地の売却価格×底地の取得価格÷土地の更地価格(時価)×5%
この算式を用いて、実際に底地の概算取得費を計算してみます。
【底地の概算取得費の計算例】
AさんはBさんから土地を借りており(借地権)その譲渡を考えていました。
借地権部分だけの譲渡では価格が低くなると考えたAさんは、Bさんから底地を購入しました。
その後、取得した底地と借地権を合わせて売却することができました。
底地と借地権の譲渡価格は「8,000万円」
底地の取得価格は「3,000万円」
土地の更地価格は「1億円」
上記の例の場合の概算取得費は下記のようになります。
8,000万円×3,000万円÷1億円×5%=120万円
借地権や底地の概算取得費を計算する際には、それぞれの計算方法を一度整理することが大切です。
土地の一部を売却した際の取得費
土地の売却をお考えの場合、その土地の売却方法は売主が決めることになります。
土地全体を売却するという場合もあれば、土地の一部を売却する場合もあります。
土地全体を売却する際には、その土地を取得した際の購入価格をそのまま取得費とします。
土地の一部を売却する場合でも、土地が元々分筆されており当時に別々に購入したものであれば、対応する分の購入価格が取得費となります。
ここで問題となるのは、当時に一括で購入した土地を分筆し、その一部を売却した場合です。
この場合、土地を分筆したということで、元々の土地の購入価格が取得費とならなくなってしまいます。
土地の一部を売却する場合には、その際の取得費の計算方法について知っておくことが大切です。
一括で購入した土地の取得費は原則、面積の比により計算を行います。
上記以外にも、売却時における「売却した土地部分」と「残部分の土地」の時価で計算をする方法もあります。
これらの詳しい説明につきましては、次の項目で詳しくご説明致します。
土地の一部の取得費を計算する方法
土地は、分筆などにより分割し、その一部を売却するといった方法を取ることもできます。
土地を一部売却する場合の取得費は、土地全体を売却した場合よりも低くなるのが一般的です。
取得費とは、その土地を取得する際に要した費用であるということを考えると、売却部分のみに対応する取得費を割り出すことが必要です。
その際の計算方法としては、土地全体と売却した土地部分の面積の比により購入価格を按分していきます。
【取得費の計算例】
以前に、土地300m²を「900万円」で購入し、その土地のうち「100²」を売却した場合の取得費
この場合の取得費は、土地の当時の購入価格である「900万円」を、売却した土地分(100²)とで按分する必要があります。
900万円÷300m²=3万円
3万円×100²=300万円
上記の計算から、この場合の取得費は「300万円」ということになります。
このように一括で購入した土地の一部を売却した際には、土地全体と売却した部分の土地の面積の比で取得費を按分するのが原則ですが、
売却した土地部分と残部分の土地の時価がそれぞれ適正に算定できる場合には、その時価により按分した価格を取得費とすることもできます。
土地の適正な時価が不明である場合には、面積により価格を按分する方法を用いて計算を行ってください。

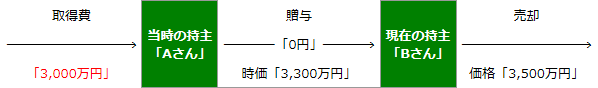 ※クリックで表示
※クリックで表示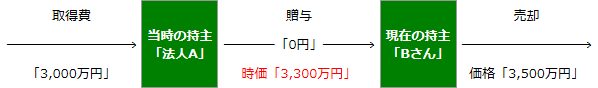 ※クリックで表示
※クリックで表示 ※クリックで表示
※クリックで表示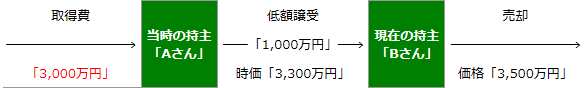 ※クリックで表示
※クリックで表示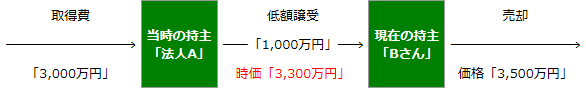 ※クリックで表示
※クリックで表示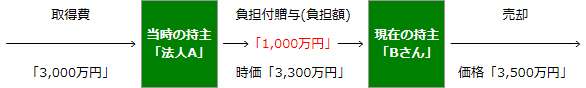 ※クリックで表示
※クリックで表示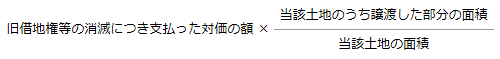 ※クリックで表示
※クリックで表示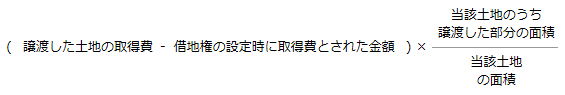 ※クリックで表示
※クリックで表示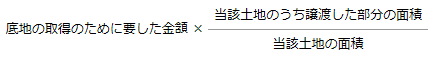 ※クリックで表示
※クリックで表示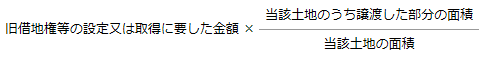 ※クリックで表示
※クリックで表示